「できる経理マン」と「ダメ経理マン」の習慣
経理で仕事をしていると、色んなタイプの経理マンに出会います。
1円単位で差額を気にする人、無駄な経費を削減しろと言い続けている人、仕事をすぐ他人にお願いしている人。
タイプは様々ですが、仕事ができる経理マンには共通した習慣があります。
経理マンの多くは、定例業務をそつなくこなし、定時退社することを目標にしているのではないでしょうか。
しかし、それだけでは「仕事はできるけど、何かもの足りない」そんな経理マンとして評価されているかもしれません。
評価を左右するのは、スキルや資格ではなく、日々の仕事の習慣にあると著者は言っています。
あなたはどんな習慣の中で仕事をしていますか?
「できる経理マンはストイック / ダメ経理マンは寛容」
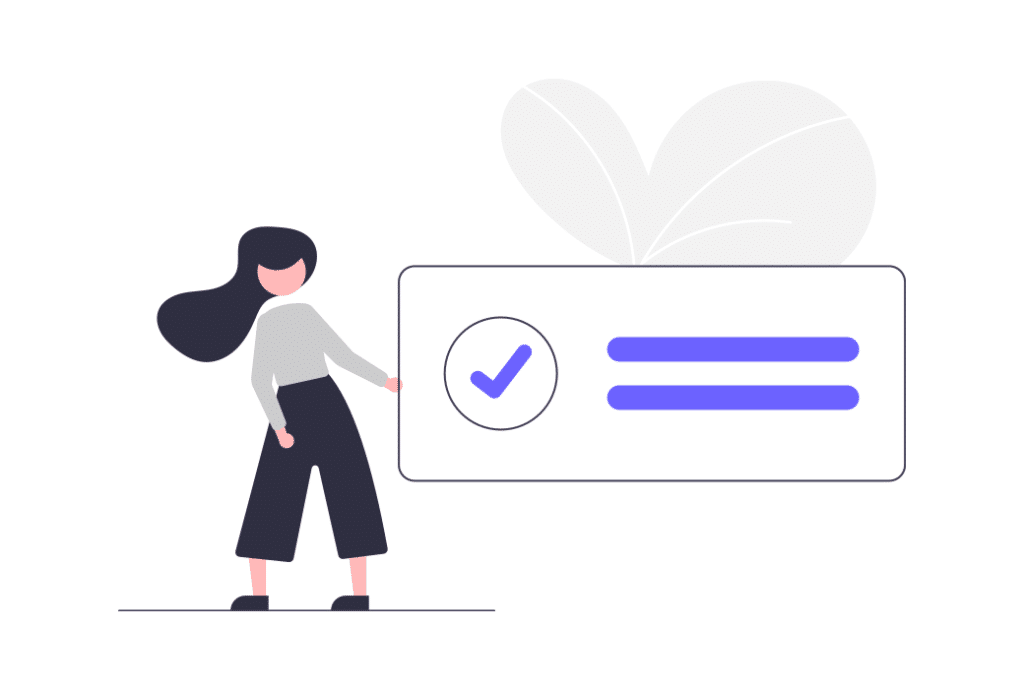
経理として仕事をしていく上で重要なことは。間違えないことです。
頻繁に仕訳を間違えたり、桁が一つ多かったり、見当違いな決算報告をしていては、正確な数字だとしても誰にも信用されず経理の存在意義がなくなってします。
チェック作業を怠ったり、貸借関係を意識しないまま作業をすることはミスの原因になります。
小さいミスの積み重ねが、決算時に明らかになり問題になることもあります。
また、よく発生する間違いというのが、どこの会社でもあると思います。
このよく間違いが発生する箇所は、仕事の仕組みで発生を抑えることができます。間違いをする人が悪いのではなく、間違いを発生させるような仕事の仕組みが悪いと考えましょう。
P.102
何かミスをしたとき、自分が注意をするという対策では解決になりません。
ミスが発生してしてしまう仕組側を改善し、絶対にミスが発生しないようにしましょう。
「できる経理マンは決算書から感じ取る / ダメ経理マンは決算書を読む」
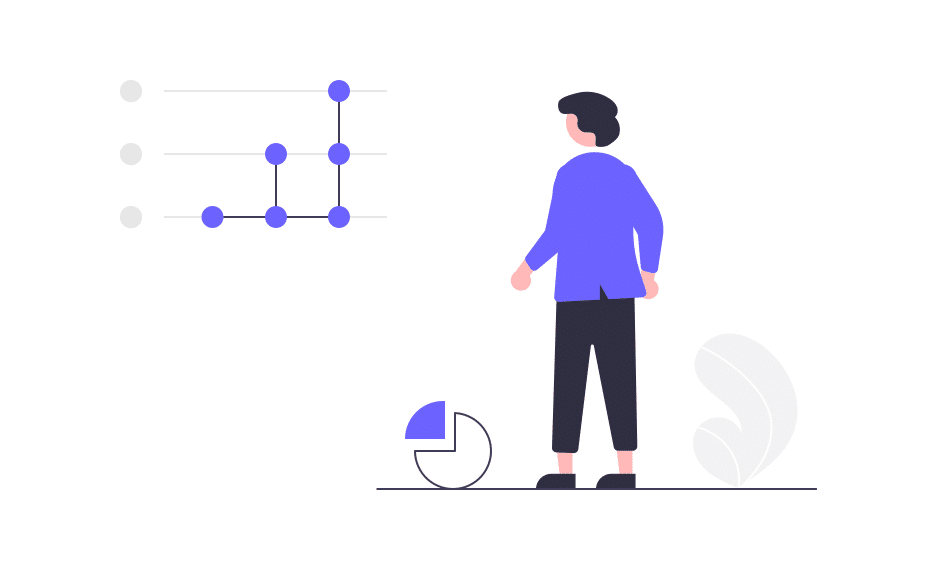
経理なら誰でも経験する決算報告。
日々の仕訳が積み重なり、決算書が完成していくわけですが、みなさんはどのように報告していますでしょうか。
決算書を完成させたことに満足し、決算報告ではただただ数字を読みだけになっていませんか?
数字を読み上げるだけなら経理でなくてもできます。
経理に求められているのは、
「決算にどんな問題があり、何をどう改善するとどんな結果になるのか」
ということを経営陣に報告することです。
売上や利益を暗記して即答できたとしても、それ自体に意味はありません。
好調なのか不調なのか。今後何をすべきなのか。
それは分析して初めてわかることですが、できる経理マンは決算書を一目見て異変に気が付くことができます。
それは、決算書をただの数字として見ているのではなく、日々の仕訳や、売上の動向の積み重ねだということを意識しながら見ているからです。
できる経理マンは、だいたいこんな感じでできあがるだろうという予想をした上で完成した決算書の分析を始めるのです。
「できる経理マンは面倒くさがり / ダメ経理マンはマメ」
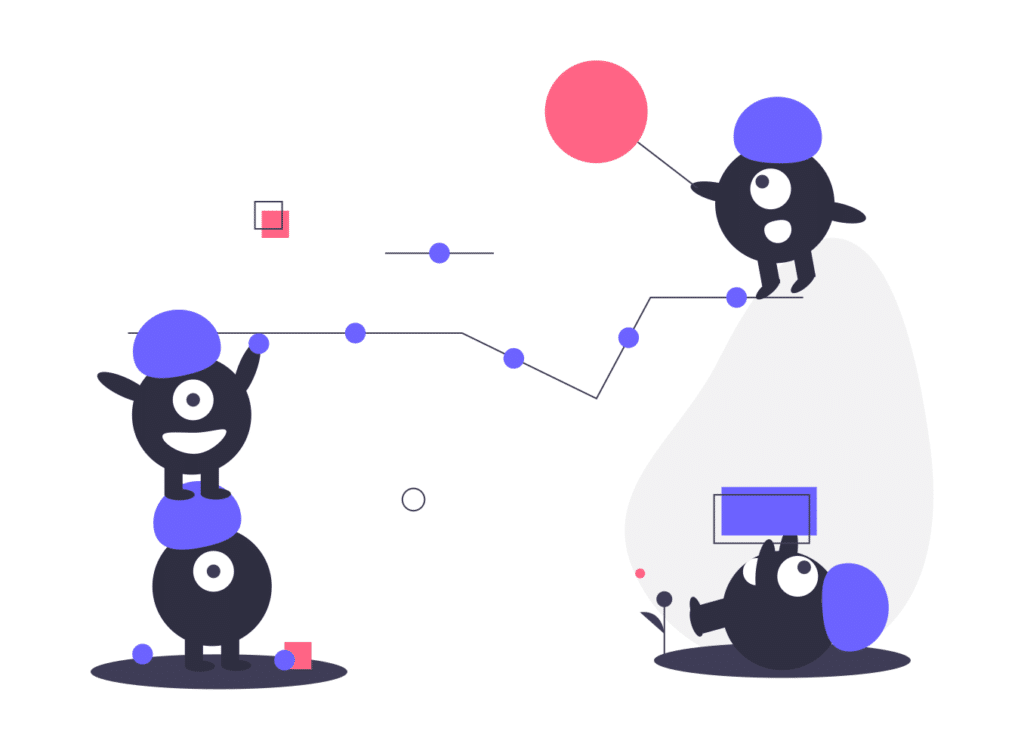
要約1で経理で大事なことは間違えないことだとお伝えしましたが、それと同じくらい大事なのは改善志向があるかどうかです。
間違えない為には、仕組みを変える必要がありますが、
ミス防止の仕組みでよく見かけるのは書類のダブルチェックです。
マメな経理マンは全ての書類に目を通し、ペンでチェックをして印鑑を押しているかもしれません。
確かに2人でチェックすればミスは減らせます。
しかし、工数が1つ増えてしまいました。また、結局人がチェックしている為ミスが発生しないという保証はできません。
そんな時面倒くさがりな経理マンはどうするのか…。
一例ですが、書類でチェックをしていた内容をExcelでチェックするようにすれば関数やExcelの機能を使ってミスを防止することができます。
仕組をつくればいいんでしょ!とチェック回数を増やしても意味はありません。
より効率的に業務を遂行する仕組みづくりをしていく必要があります。
さらに面倒くさがりな経理マンは、作業を標準化させ誰でもできるようにします。
月次決算や予実管理など、重たい業務も細分化すれば細々とした単純作業で構成されています。
できあがった数字を分析するのは経理でないと難しいかもしれませんが、単純作業部分に関しては誰でもできるものがほとんどではないでしょうか。
Excelでのデータ加工やシステムからの帳票のダウンロード、書類の印刷など。
単純作業を他の人に引継ぎ、自分は分析を行う。
こうすることで、突発的な引継ぎであせって手順書をつくる必要もなくなり、作業量を減ったことでミスが発生する可能性も減らすことができます。
実践ポイント
✅ヒューマンエラーは仕組化と標準化で防止する。
✅標準化された単純作業は他人に任せ、経理でないとできない仕事に注力する。
✅数字の根拠、決算書を見る感覚を身につけ、経営陣にとって役に立つ情報を提供する。